なぜ今、“お金の勉強”が必要なのか
毎日忙しく働いているのに、なかなか貯金が増えない。
将来のことを考えると、ふと不安になる——。
そんな看護師さんは多いのではないでしょうか。
「お金の勉強」と聞くと、少し堅いイメージがありますが、
実は私たちの生活や仕事に、とても深く関わっているテーマです。
この授業では、看護師がなぜ“お金の知識”を身につける必要があるのかを、一緒に考えていきましょう。
お金の使い道を知ることから始めよう
まず、「お金を使う」とはどういうことかを考えてみます。
お金の使い道は大きく分けると2つ──
物を買うか、サービスを買うか、です。
病院は物を売っているわけではないので、私たちは「医療というサービス」を提供しています。
「医療はサービス業ではない」と感じる方もいるかもしれませんが、
分類するなら、医療も“サービス”に含まれます。
つまり、私たちの働く現場も「経済活動の中の一部」なのです。
医療とお金を取り巻く現実:2025年問題とは
皆さんも一度は聞いたことがあると思います。
2025年問題――団塊の世代が全員75歳以上となり、国民の5人に1人が後期高齢者になる年です。
その結果、社会全体で次のような問題が懸念されています。
- 社会保障費の増大
- 医療・介護体制の維持困難
- 労働力不足と経済の停滞
社会保障費は年々増加している一方で、少子化により現役世代は減少しています。
つまり、現役世代(=私たち)が負担する保険料や税金は、今後さらに増えていく見込みです。
病院のベッド数も足りなくなり、国は「病院から在宅へ」という流れを進めています。
また、社会保障費の中でも医療費の割合はとても大きいため、
医療をいかに効率的に・必要な範囲で提供していくかが課題になっています。
現場にも影響が…病院経営と看護師の働き方
医療機関の収入は「診療報酬」で定められており、定期的に改定されています。
しかし、今後はプラス改定が難しい時代になるかもしれません。
収入が増えにくい中で、人件費を含む支出を抑える必要があるため、
「少ない人員で現場を回す」という状況はさらに進むでしょう。
「もうすでにそうなっているよ」と感じる方も多いかもしれません。
現場の負担が増える一方で、給与はなかなか上がらない。
病院も生き残るために経営を考え、私たち看護師も“どう働き続けるか”を考える必要があるのです。
個人としてできること:お金を「学ぶ」という選択
国の政策や病院経営の方針は、私たち個人がすぐに変えられるものではありません。
でも、自分のお金の知識や行動は、今すぐ変えられます。
- 家計を整える
- 投資や資産運用の基礎を学ぶ
- 収入源を増やす方法を知る
こうした知識は、「働き方を選ぶ力」や「将来の安心」につながります。
お金を学ぶことは、自分と家族を守る力を身につけることなんです。
まとめ:一緒に“お金の教室”をはじめましょう
社会全体の変化は止められません。
けれど、変化の中で自分を守るための「知識」は身につけられます。
このブログ「看護師のお金の教室」では、
看護師としてのリアルな現場と、お金の基礎知識をつなげながら、
無理なく・楽しく学べる“授業”をお届けしていきます。
次回は、「お金の流れ」をもっと身近な視点から見ていきましょう。
今日から一緒に、“看護師のお金の教室”を始めましょう。
次の記事はこちら 👉 お金の基礎知識②|インフレとは?看護師の給料と物価の関係をやさしく解説
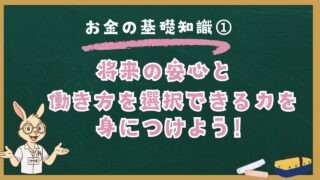
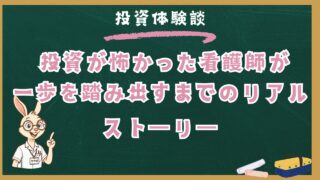
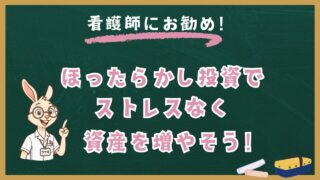
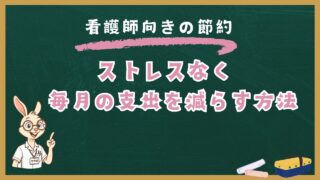
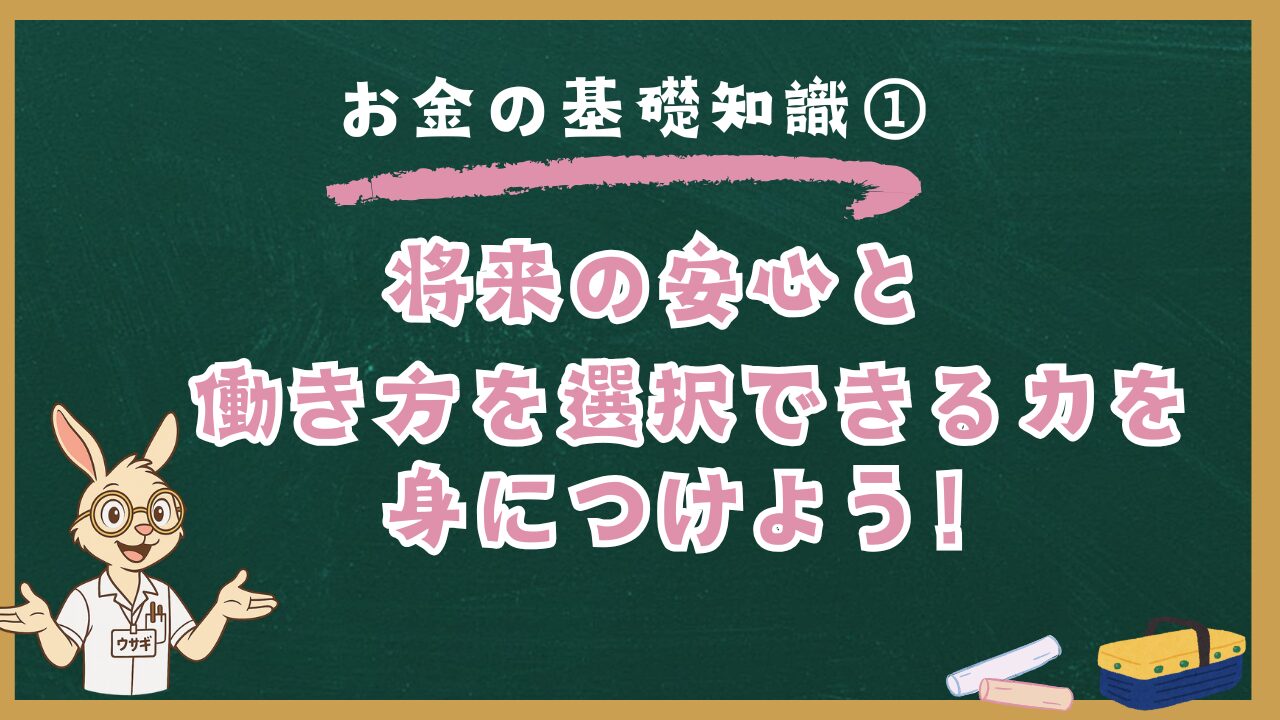
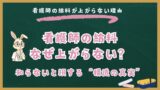

コメント