導入:ニュースでよく聞く「円安」って結局なに?
ニュースで「円安が進んでいます」と聞くこと、増えましたよね。
でも、「なんとなく損している気がするけど、よくわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そもそも円安とはどういうことか。
そして、円安が私たち看護師の生活にもどう影響しているのかを、わかりやすくお話していきたいと思います。
円安とは?
円安とは、日本円の価値が外国の通貨に対して下がることです。
たとえば、1ドル=100円だったのが、1ドル=150円になる。
このとき、「円安になった」と言います。
つまり同じ1ドルを買うのに、前より多くの円が必要になっている——
これが「円の価値が下がる」ということなんです。
円安になると何が起こる?
円安になると、日本にとって良いことも悪いこともあります。
それを理解するために、「海外とのお金の流れ」を少し見てみましょう。
円安で困ること
- 輸入品の価格が上がる(=生活費が上がる)
→ 食料品、ガソリン、電気、衣類など、海外から入ってくるものが高くなる - 海外旅行の費用が上がる
→ 同じドルやユーロを買うのに、より多くの円が必要になる
円安で得すること
- 輸出企業が有利になる
→ 海外での売上が円換算で増えるため、トヨタなど輸出型企業は利益アップ - 外国人観光客が増える
→ 「日本の物価が安い」と感じてもらえるため、観光業にはプラス
つまり円安には、「輸入にはマイナス」「輸出にはプラス」という二面性があります。
しかし、私たちの生活者目線では“支出が増える方向”に働くことが多いのです。
看護師の生活にどう関係するの?
一見、円安は「企業や国の話」で、自分には関係ないように思えますよね。
でも実際には、看護師の生活・給料・職場環境にも大きく関係しています。
生活費の上昇
輸入品の値上がりは、食費・光熱費・ガソリンなどに直結します。
特に医療用品やエネルギーコストの上昇は、病院経営にも影響します。
iPhoneの値上がりも円安が原因?
日本人はiPhoneを使っている人が多いですよね。
皆さんもiPhone使ってます?
昔は10万円以下で買えたのに、今は15万円以上します。
毎年新製品が発表されていますが、「もう高くて買えない!」と思う方も多いのではないでしょうか。
気軽に買えるスマホではなくなった——そんな印象ですよね。
でも、実はアメリカではiPhoneの値段はほとんど変わっていないんです。
日本で販売されるiPhoneが高くなったのは、まさに円安の影響。
同じ製品でも「円の価値」が下がることで、価格が上がって見えるのです。
資産運用との関係
私自身、お金の勉強を始めるまでは、円安や円高は自分の生活に関係ないと思っていました。
しかし、海外株式投資やFXを学ぶ中で、インフレや金利政策と密接に関わっていることを知りました。
つまり、円安を理解することは「資産を守る」ことにもつながるのです。
看護師の仕事にも影響がある?
もっと身近なところでは、看護師の仕事の中にも円安の影響を感じる場面があります。
私は病院の委員会活動で業者さんとやり取りをする機会がありましたが、
「仕入れ価格が円安で上がっている」「今後はもっと値上がりするかもしれない」
——そんな話を聞くたびに、設備や医療物品も世界の経済とつながっていることを実感しました。
昔は無関係だと思っていた“円安”が、実は看護師の仕事や生活と深く関係しているのです。
病院経営への影響
医療機器や医薬品の多くは海外製です。
円安によって仕入れコストが上がると、病院の支出が増加します。
しかし診療報酬はすぐには上がらないため、結果的に人件費の抑制や経営の圧迫につながることもあります。
給料の「実質的な価値」が下がる
円安によって物価が上がる=同じ給料でも買えるものが減るということ。
つまり、給料の実質的な価値が下がるのです。
これはインフレの影響とも重なり、生活の余裕を奪う要因になります。
円安が進む理由をやさしく解説
円安は「外国為替市場」という場所で決まります。
1ドル=何円、というレートは、世界中の投資家がお金を売買する中で日々変動しているのです。
では、なぜ円が売られやすくなるのでしょうか?
① 日本の金利が低いから
他国(特にアメリカ)の金利が高いと、投資家は利息の高い国にお金を移します。
その結果、円が売られてドルが買われる → 円安が進むという流れになります。
② 貿易赤字が続いているから
日本はエネルギーや食料を多く輸入しています。
輸入が増えると、円を使って外国の通貨を買う必要があり、これも円安の一因になります。
③ 景気や投資マインドの影響
「今の日本はあまり成長していない」と見られると、海外からの投資が減り、円が売られやすくなります。
円安の時代にどう行動する?
円安を“止める”ことはできませんが、備えることはできます。
- 家計の支出を見直す(家計防衛)
→ 食費・光熱費など、インフレ対策と同じく固定費管理を意識する - 円だけに頼らない資産形成
→ 外貨建て資産・投資信託・海外ETFなどを少しずつ学んでみる - 情報に触れる習慣をつける
→ 為替ニュースや日銀の動向に少し関心を持つだけで、見える世界が変わります
「お金の動き=世の中の動き」だと理解できるようになると、
日々のニュースも“自分ごと”として感じられるようになります。
まとめ:世界の動きが、自分の生活を変える
円安は、国のニュースのようでいて、実は私たちの日常の財布の中にもつながっています。
給料の価値、物価、病院経営、働き方——すべてが少しずつ影響を受けています。
看護師として働く私たちも、経済の流れを知っておくことが「自分を守る知識」になります。
円安をきっかけに、「世界とお金のつながり」を少しずつ学んでいきましょう。
次の記事はこちら 👉 お金の基礎知識④|金利とは?貯金・ローン・投資にどう関係するのか
お金を借りる・貯める・増やす——すべてに関わる“金利の基本”を、やさしく解説します。
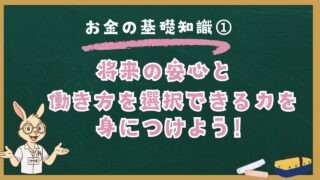
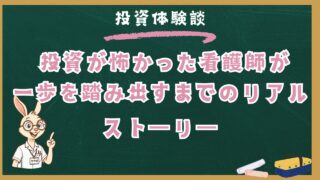
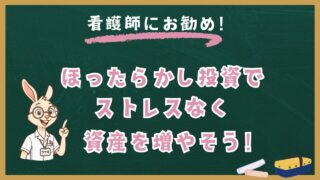
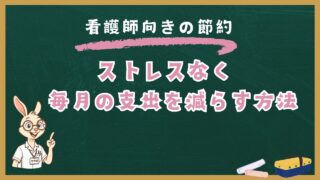
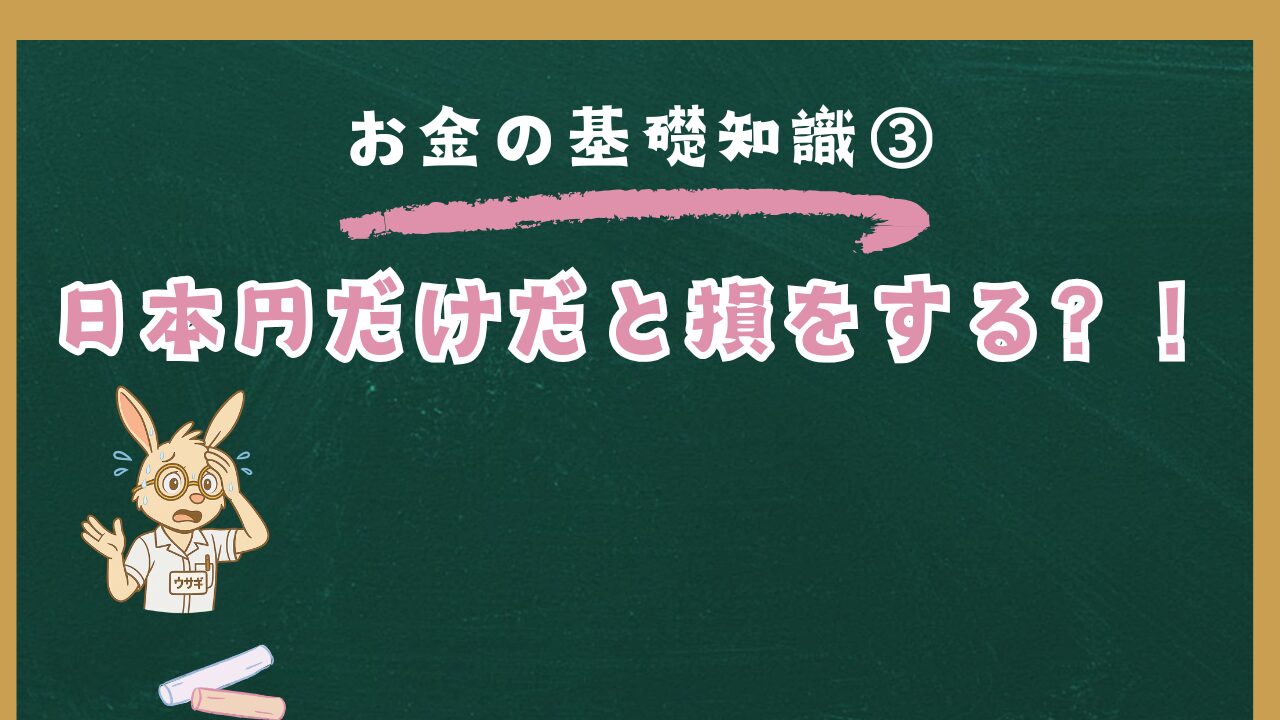


コメント