最近、なんでも値上がりしていませんか?
スーパーに行くたびに、「前より高くなったな…」と思うこと、ありませんか?
食料品、光熱費、ガソリン——生活に関わるものが次々と値上がりしています。
それが、いま私たちが実感しているインフレ(物価上昇)です。
看護師として毎日働いていても、給料がすぐに上がるわけではありません。
「なんとなく損をしている気がする…」
そんなモヤモヤを感じている方も多いでしょう。
この授業では、「インフレとは何か」「なぜ起こるのか」、そして「看護師の生活や給料にどう関係するのか」を、やさしく整理していきます。
インフレとは?お金の価値が下がること
インフレ(inflation)とは、物の値段が上がり、お金の価値が下がることをいいます。
たとえば、去年100円で買えたお菓子が、今年は120円になっていたとします。
同じお菓子なのに値段が上がったということは、100円ではもう買えなくなった=お金の価値が下がったということなんです。
つまりインフレとは、
という現象です。
実感としてのインフレ:私自身の体験から
私が車の運転免許を取ったばかりの頃、ガソリン代は1リットルあたり88〜92円くらいでした。
それが今では180円を超えることも珍しくありません。
(※2025年末にガソリン暫定税率廃止が決定しました。2025年12月では1リットルあたり140円台くらいとなりました。)
看護師になった当初と比べても、税金や社会保険料は上がり、物価も上がっています。
もちろん名目上の給料は増えましたが、消費税や年金・保険料などの負担が大きくなり、手取りで見るとほとんど増えていません。
「給料が減っているわけではないけれど、買えるものが減っている」——
この感覚こそ、まさにインフレによる実質所得の低下なんです。
私は以前、夜勤のときにコンビニで飲み物や軽食を買うのが日課でした。
でも最近は値上がりを実感して、コンビニにはほとんど行かなくなりました。
同じ働き方をしていても、支出の感覚が変わってきたと感じます。
なぜインフレが起きるのか?
インフレが起こる理由は一つではありません。代表的な原因を3つ挙げてみましょう。
① コストプッシュ型インフレ
原材料や人件費などの「コスト」が上がることで、商品の価格も上がるタイプです。
たとえば輸入小麦の値上がりや、光熱費の上昇などがこれにあたります。
最近の日本は、この「コストプッシュ型インフレ」が多く見られます。
② 需要(じゅよう)増加型インフレ
景気が良くなり、人々が「もっと買いたい」と思うことで、需要が増えて値段が上がるタイプです。
観光業や外食など、人が動くと発生しやすいです。
③ 金融政策によるインフレ
国や中央銀行(日銀)が金利を下げたり、お金を多く流通させることで起こるタイプです。
お金が世の中に増えると、結果的に物価が上がりやすくなります。
インフレが看護師の生活に与える影響
では、インフレが進むと、看護師の生活はどう変わるのでしょうか?
実は、収入が変わらなくても「実質的な生活レベル」が下がることがあります。
- 食料品・生活用品の値上がり
- 光熱費・交通費の上昇
- 家賃や住宅ローン金利の上昇(将来的に)
つまり、同じ給料でも「使えるお金」が減るということです。
この状態を「実質所得が減る」といいます。
病院経営にも影響するインフレ
インフレは個人の生活だけでなく、医療現場にも影響します。
たとえば、医療機器や医薬品の仕入れ価格が上がると、病院のコストも増えます。
しかし、病院の収入源である診療報酬は簡単に上がらないため、
という構造になります。
結果として、人件費の抑制や現場の負担増につながることも。
看護師としても、経済の動きを知っておくことは「働き方を考える力」につながります。
デフレとは?(対比して理解しよう)
インフレの反対が「デフレ(デフレーション)」です。
物の値段が下がり、お金の価値が上がる現象を指します。
一見「物価が下がるなら良いこと」と思いがちですが、
企業の利益が減ることで、給料が上がらなくなり、景気が停滞するというデメリットもあります。
日本は“長いデフレ時代”を経験してきた
実は日本は、1990年代後半から約20年以上もの間、デフレ傾向が続いてきました。
そのきっかけは、1980年代のバブル経済が崩壊したことにあります。
土地や株の価格が急落し、企業も個人も大きな損失を抱えました。
将来への不安から、企業は投資や賃上げを控え、個人もお金を使わなくなったのです。
ものを買う人が減ると、企業は少しでも売るために値下げを続けるしかなくなり、物価が下がり続ける“デフレスパイラル”に陥りました。
つまり、日本のデフレは「みんなが将来に不安を感じてお金を使わなかった結果、景気が冷え込んだ」という、心理的な面も大きかったのです。
そして今、日本は“インフレの時代”へ
しかし近年は、円安やエネルギー価格の高騰、海外の物価上昇の影響などから、
日本でも明確にインフレが起きる時代へと変化しています。
これまで「物価が上がらないこと」が当たり前だった私たちにとって、
「値上がりが続く社会」は大きな転換点です。
今はまだ“緩やかなインフレ”ですが、
給料や医療現場のあり方、将来の資産形成を考えるうえで、
この変化を理解しておくことがとても大切です。
インフレの時代にどう備えるか?
インフレは避けられません。
でも、備えることはできます。たとえば──
- 家計の固定費を見直す(通信・保険・光熱費)
- 資産を「現金だけ」で持たない(貯金+投資のバランスを考える)
- お金の勉強を続ける(制度・税金・経済の基本を知る)
インフレは悪いことばかりではなく、経済を活性化させる面もあります。
大切なのは、「自分の生活とどう関係しているか」を理解し、行動につなげることです。
まとめ:インフレを知ることは、自分を守ること
看護師は「人の健康を守る仕事」ですが、
これからは「自分の生活を守る知識」も大切です。
インフレはニュースの中だけの話ではなく、
毎日の買い物、給料、働き方にも関わってきます。
この授業をきっかけに、「お金の流れ」を少し身近に感じてもらえたら嬉しいです。
次回は、「円安」について学んでいきましょう。
私たちの給料や生活が、世界の動きとどうつながっているのかを一緒に見ていきます。
次の記事はこちら 👉お金の基礎知識③|円安とは?円の価値が下がると看護師の生活にどう影響する?
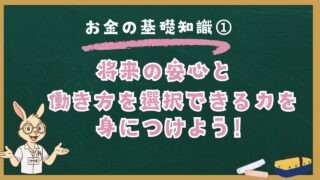
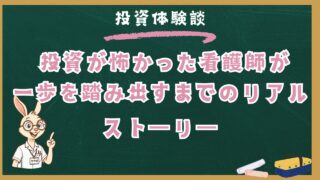
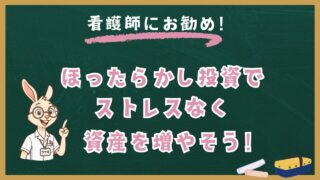
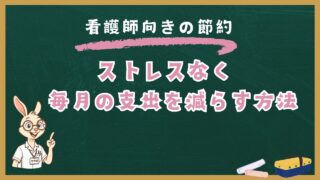
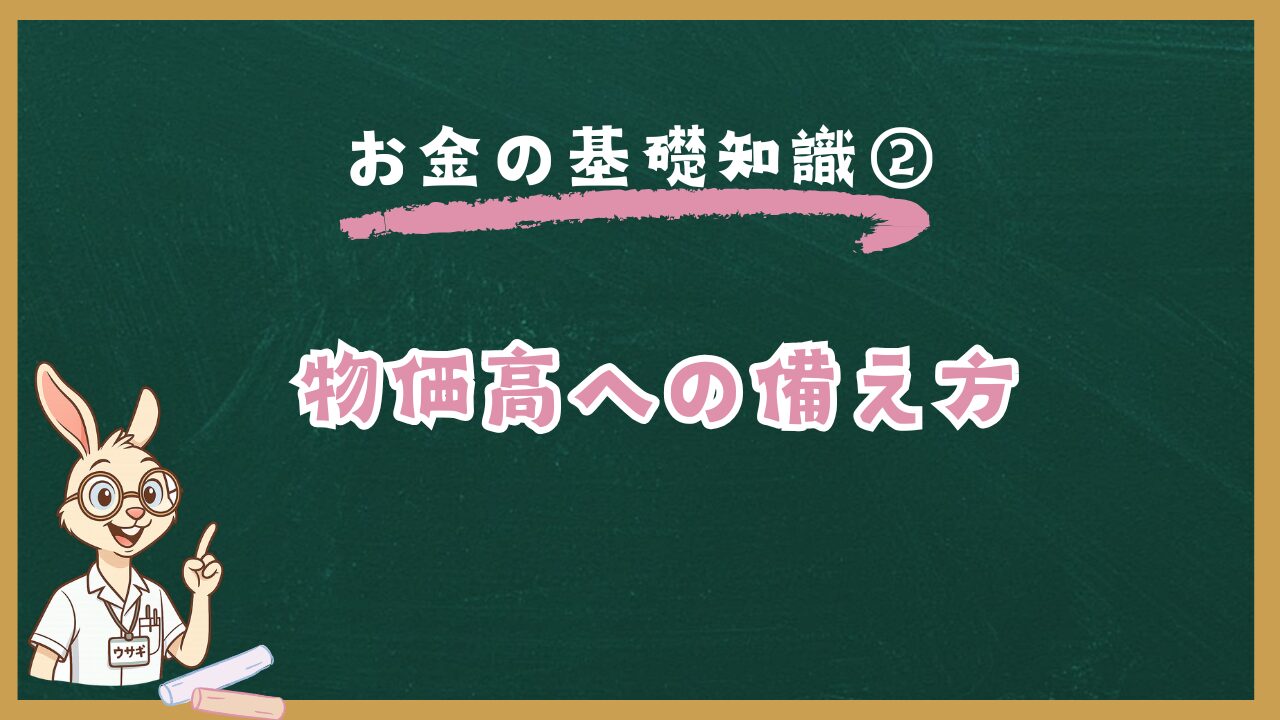


コメント