導入:ニュースで聞く「金利が上がる」ってどういうこと?
ニュースで「金利が上がる」「日銀が政策金利を据え置き」といった言葉を耳にすることはありませんか?
でも、実際の生活にどう関係するのか、ピンとこない方も多いと思います。
金利とは、お金の“レンタル料”のようなもの。
お金を借りた人が払う「利息」であり、預けた人が受け取る「お礼」です。
つまり、「お金を借りる側」と「貸す側」で意味が少し違います。
この授業では、金利の基本から、看護師の生活やお金の運用にどう影響するのかまで、やさしく解説していきます。
金利とは?お金を貸したり借りたりするときの代金
たとえば、あなたが1万円を1年間、誰かに貸したとします。
1年後に「1万100円」返ってきたら、その100円が利息(=金利)です。
つまり金利とは、
金利が高い=お金を借りるコストが高くなる
金利が低い=お金を借りやすくなる
という関係になっています。
なぜ金利は変動するの?
金利を動かしているのは「日本銀行(日銀)」です。
日銀は、景気をコントロールするために金利を上げ下げしています。
🟢 金利を下げるとき
景気を刺激したいとき(=お金を動かしたいとき)に行われます。
お金を借りやすくして、企業や個人の消費を促します。
例:コロナ禍など、不況の時期
🔴 金利を上げるとき
物価が上がりすぎているとき(インフレのとき)に行われます。
お金を借りにくくして、経済の過熱を抑える目的です。
例:現在のようにインフレ傾向が続く時期
つまり金利は、「お金の流れを整える温度計」のような存在なんです。
日本はなぜ“超低金利”だったの?
実は日本は、長い間「超低金利」の時代が続いてきました。
その背景には、バブル崩壊後のデフレ(物価が上がらない時代)があります。
企業も個人も将来が不安でお金を使わなくなり、経済を回す力が弱まってしまったのです。
そこで日銀は、「お金を借りやすくする=経済を動かす」ために金利を極端に下げました。
これがマイナス金利政策です。
銀行が日銀にお金を預けると逆に“手数料”を取られる仕組みで、企業や個人にお金を貸し出させる狙いがありました。
しかし近年、物価や賃金が少しずつ上がり始め、経済が動き出したことで、
いまは「金利正常化の時代」へと移行しています。
金利が再び上がる方向に向かっているのです。
金利が変わると、何が変わるの?
金利が上がる・下がることで、私たちの生活や経済全体が動きます。
代表的な影響を3つ見てみましょう。
① 貯金の利息が変わる
銀行の普通預金の金利は、今ほとんどゼロに近い状態です。
でも金利が上がると、預けているお金にも利息がつきやすくなります。
「貯金で少しずつ増える時代」が戻ってくるかもしれません。
② ローンの返済額が変わる
住宅ローンや教育ローンなど、借りるお金にも影響します。
金利が上がると、同じ金額を借りても返済総額が増えることに。
金利の動向を知っておくことは、「借り方を守る知識」にもなります。
③ 投資商品の値動きが変わる
金利が上がると、株価や債券の価格にも影響します。
たとえば、金利上昇は株式市場にとってマイナス材料になることもあります。
投資をしている人にとっても、金利はとても重要なサインです。
住宅ローンと金利:変動が主流の日本
日本では、住宅ローンを変動金利型で借りる人が約7割(およそ70〜75%)を占めています。
理由は、固定よりも当初の金利が低く、月々の返済額が少なく済むからです。
実際、私自身も家を建てた際に変動金利で融資を受けました。
当時は「これ以上金利は上がらないだろう」と思っていましたが、
現在では借りた当時の約2倍の金利になっています。
変動金利の場合、金利が上がると返済額も増えますが、
日本の住宅ローンには「5年ルール」と「125%ルール」という仕組みがあります。
- 5年ルール:金利が変わっても、5年間は返済額が変わらない
- 125%ルール:6年目以降に返済額が見直されるが、最大でも前回返済額の1.25倍まで
つまり、急に返済が跳ね上がることはありませんが、
長期的に見ると負担がじわじわと増える可能性があります。
看護師の生活に関係ある?金利の影響3つ
① 預金や定期貯金
金利が上がれば、銀行預金の利息が少し増えます。
「金利0.001%」が「0.1%」になるだけでも、10万円預けると利息が100円→1,000円に。
小さな差でも、長期では大きな違いになります。
② 住宅ローン
看護師の給料は他職種に比べて安定していますが、大きく上がりにくい傾向があります。
そこに金利上昇が重なれば、返済額が増え、家計を圧迫する可能性も。
さらにインフレや円安が続けば、生活コスト全体も上がり、
「収入は増えないのに支出だけ増える」状況に直面するかもしれません。
③ 投資や資産運用
金利が低い時期は、預金ではお金が増えにくいため、投資の注目度が高まりました。
しかし今後は、金利上昇によりリスク資産から安全資産へ資金が移動する流れも考えられます。
時代の流れに合わせて運用の見直しが必要です。
金利とどう付き合う?これからの考え方
金利は“敵”ではなく、“経済のバロメーター”です。
上がったり下がったりする理由を知るだけで、家計の判断力が高まります。
🔹 これからのポイント
- 「固定金利」「変動金利」の違いを理解する
- 預金・ローン・投資のバランスを考える
- ニュースの金利情報に関心を持つ
お金の知識は、一度学ぶと一生役立つスキルです。
金利をきっかけに、経済の仕組み全体を俯瞰して見られるようになります。
まとめ:お金にも“時間の流れ”がある
金利は、「お金を一定の期間、貸したり借りたりするときの代金」。
預ける人にお礼が入り、借りる人が利用料を払う──
その仕組みがあるからこそ、お金は社会の中を巡っています。
看護師として毎日働く私たちにとっても、
金利を理解することは「お金に振り回されない力」を身につける第一歩です。
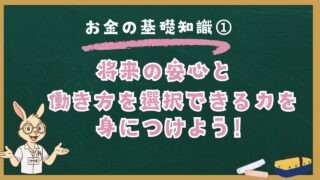
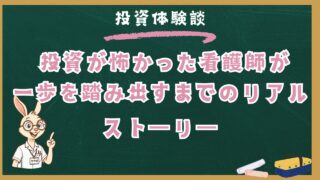
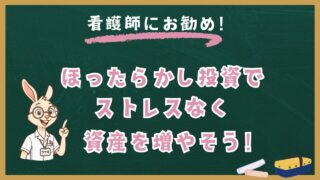
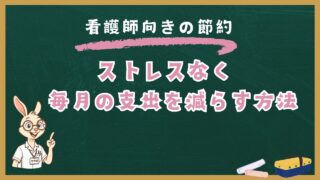
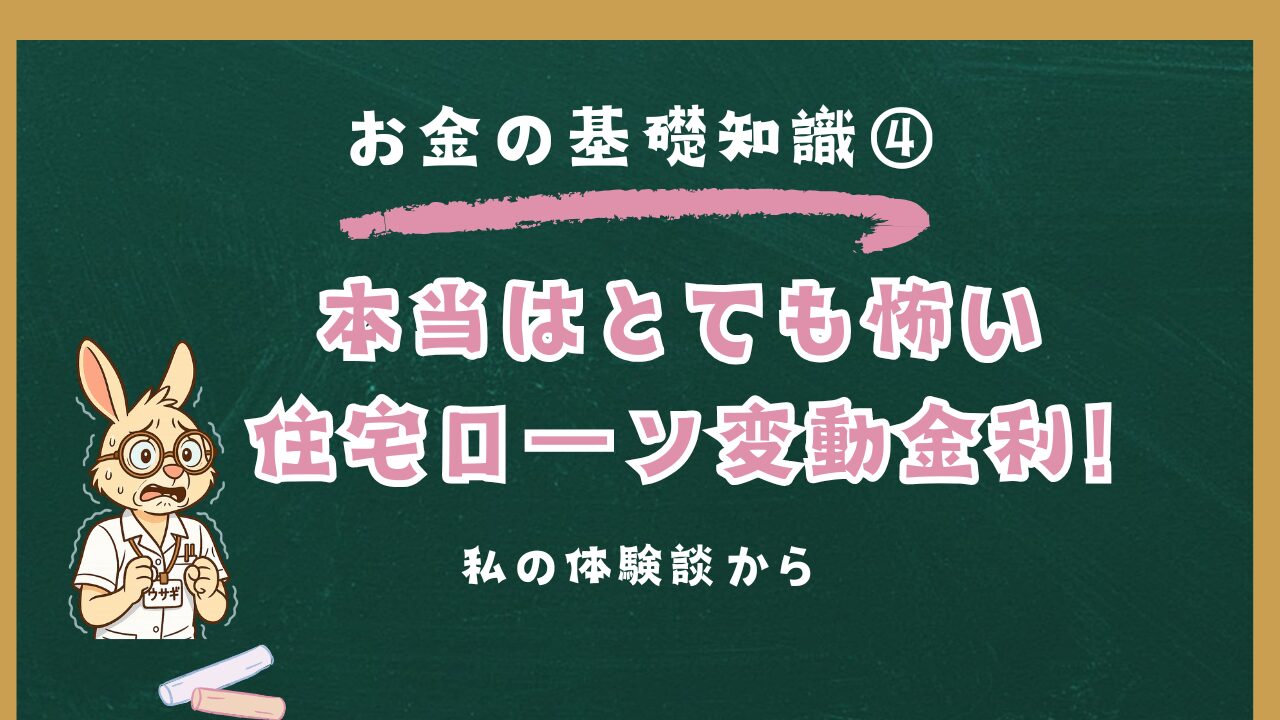

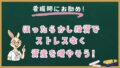
コメント